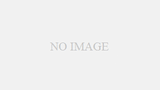離婚をする際、最も重要な問題のひとつが財産分与です。結婚生活で築いた財産は、離婚時に公平に分けることが原則となりますが、その分け方や割合について不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、財産分与の基本、計算方法、基準、注意点について詳しく解説します。
1. 財産分与とは?
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚時に分けることを指します。
日本の法律では、夫婦は対等な立場にあるため、財産分与の際も公平な分配が求められます。
① 財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に形成された財産です。
- 預貯金
- 不動産(自宅・土地など)
- 車
- 株式・投資信託
- 年金(厚生年金の分割)
② 財産分与の対象にならない財産(特有財産)
婚姻前に持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は、財産分与の対象になりません。
- 結婚前に持っていた預貯金
- 親から相続した不動産や資産
- 個人名義の保険金(婚姻期間中の支払い分を除く)
2. 財産分与の割合はどう決まる?
基本的に、財産分与の割合は「2分の1ルール」が適用されます。
① 2分の1ルールとは?
原則として、夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、夫婦が平等に貢献したとみなされ、半分ずつ分けるのが基本です。
これは、専業主婦(主夫)であったとしても、家庭内での労働が経済的貢献とみなされるためです。
② 例外的に割合が変わるケース
ただし、以下のような場合は財産分与の割合が変わることがあります。
- 夫(または妻)が個人の事業を経営していた場合
- 財産形成への貢献度に大きな差がある場合
- 不貞行為やDVなど、離婚原因に相手の過失がある場合
3. 財産分与の計算方法
財産分与の計算は、次のようなステップで行います。
① 夫婦の財産をリストアップ
- 銀行口座の残高を確認
- 不動産の評価額を調査
- 車や貴金属などの価値を算出
② 共有財産と特有財産を区別
- 婚姻期間中に形成されたものが「共有財産」
- 婚姻前の財産・相続財産は「特有財産」
③ 2分の1ルールに基づき分配
- 夫の名義で預貯金が1000万円ある場合 → 妻は500万円を受け取る
- 自宅不動産(評価額3000万円)がある場合 → 売却して1500万円ずつ分配、または一方が住み続けて代償金を支払う
4. 財産分与の注意点
① 相手が財産を隠していないか確認
離婚時には、相手が財産を隠すケースもあるため、通帳や証券口座の履歴をしっかり確認しましょう。
② 住宅ローンが残っている場合の対応
住宅ローンが残っている場合、以下の対応が考えられます。
- 家を売却し、ローンを完済する
- どちらかが住み続け、ローンを引き継ぐ
③ 年金分割の手続きを忘れない
離婚後に、夫(または妻)の厚生年金を分割することができます。
- 婚姻期間中の厚生年金を分割可能
- 家庭裁判所での手続きが必要
5. 財産分与の手続き
① 協議離婚の場合
- 夫婦で話し合い、財産分与の合意をする
- 公正証書を作成し、合意内容を明文化する
② 調停離婚の場合
- 家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てる
- 調停委員を通じて財産分与の交渉を行う
③ 裁判離婚の場合
- 調停が不成立になった場合、裁判で財産分与の決定を求める
- 裁判所の判決に基づき財産を分配
まとめ
離婚時の財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を公平に分けることが原則です。
財産分与の計算方法は、基本的に2分の1ルールが適用されますが、財産の種類や状況によって変動することもあります。
離婚後の生活を守るために、財産のリストアップ、分与方法の検討、公正証書や調停の活用をしっかり行いましょう。
また、相手が財産を隠していないか確認し、必要に応じて弁護士のサポートを受けることも重要です。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
お金・財産・住宅ローンの整理