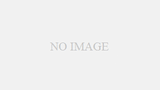離婚後に子どもを養育する親にとって、養育費は子どもの生活を支える重要な資金です。しかし、適正な金額の決め方や未払いのリスクについて、不安を感じる方も多いでしょう。本記事では、養育費の決め方、計算方法、未払いを防ぐための対策について詳しく解説します。
1. 養育費とは?
養育費とは、離婚後に子どもを育てる親(監護親)が、もう一方の親(非監護親)から受け取る経済的支援のことを指します。養育費には以下のような費用が含まれます。
- 食費や衣類代
- 教育費(学校・塾・習い事など)
- 医療費
- 住居費
2. 養育費の決め方
養育費の金額は、夫婦間の合意または家庭裁判所の基準に基づいて決定されます。
① 養育費算定表を参考にする
日本では、家庭裁判所が作成した「養育費算定表」が広く利用されています。この表は、両親の年収と子どもの人数・年齢に基づいて適正な養育費を示しています。
例えば、父親の年収が400万円、母親の年収が200万円、子どもが1人(0~14歳)の場合、養育費は月4~6万円程度が相場となります。
② 夫婦間の話し合いで決める
家庭裁判所の基準を参考にしながら、夫婦間で合意することも可能です。
- 子どもの教育方針に応じて養育費を増額する
- 大学進学を考慮し、成人後まで支払うよう設定する
③ 調停・裁判で決める
夫婦間で合意できない場合、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることができます。調停が成立しなければ、裁判で養育費の金額が決められます。
3. 未払いを防ぐための対策
養育費の支払いを確実にするためには、以下の対策を講じることが重要です。
① 公正証書を作成する
養育費の取り決めは公正証書にすることで、強制執行が可能になります。
- 公正証書には「支払いが滞った場合、強制執行を行う」旨を記載
- 裁判なしで給与差し押さえが可能になる
② 直接支払いではなく口座振込を指定する
養育費の支払い方法を口座振込にすると、支払い履歴が残り、未払いが発生した場合の証拠になります。
③ 養育費保証制度を利用する
養育費の未払いを防ぐため、養育費保証会社を利用する方法もあります。
- 保証会社が養育費を立て替え、非監護親から回収
- 一定の手数料がかかるが、未払いリスクを減らせる
④ 強制執行の準備をしておく
養育費の支払いが滞った場合、給与や預金を差し押さえることができます。
- 公正証書があれば裁判なしで執行可能
- 裁判所に申し立てれば、未払い分を回収できる
⑤ 行政の支援を活用する
養育費の未払いで困ったときは、自治体の養育費相談窓口を利用できます。
- 無料で弁護士相談を受けられる
- 公正証書の作成支援
4. 養育費の支払い期間と変更
養育費は通常、子どもが成人するまで(20歳)支払われます。ただし、以下のような場合には変更が可能です。
① 養育費を増額・減額する場合
以下のような事情があれば、養育費の増額や減額を請求できます。
- 親の収入が大幅に変化した(失業・昇給など)
- 子どもが私立大学に進学し、教育費が増えた
② 養育費の支払いを終了するケース
- 子どもが20歳になった
- 子どもが就職し、経済的に自立した
ただし、成人後も大学進学などの事情があれば、話し合いで継続するケースもあります。
5. 養育費の支払いトラブルを防ぐために
養育費の未払いを防ぐためには、最初の取り決めが重要です。
① 支払い方法を明確にする
振込先や支払い期日を決め、文書で残しておきましょう。
② 定期的に状況を確認する
支払いが滞らないよう、必要に応じて相手と連絡を取ることも大切です。
③ 未払いが発生したらすぐに対応する
数ヶ月の未払いを放置すると、回収が難しくなるため、早めに対処しましょう。
まとめ
養育費の決め方には、養育費算定表を参考にしたり、公正証書を作成するなどの方法があります。未払いを防ぐためには、口座振込を利用し、必要に応じて強制執行や保証制度を活用することが重要です。養育費は子どもの成長に不可欠な資金であるため、確実に受け取れるよう適切な対策を講じましょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
お金・財産・住宅ローンの整理